2024.09.24
不動産売却
相続した不動産を売却する前に知っておくべき5つのポイント

相続した不動産を売却することを考えている方にとって、手続きや税金の問題は悩ましいものです。相続は突然訪れることが多いため、何から手をつけていいのか分からず、困惑してしまうことも少なくありません。この記事では、相続した不動産を売却する際に知っておくべき5つの重要なポイントについて解説します。
まず、相続が発生すると誰が相続するのかを確認する必要があります。法律により決められた「法定相続人」が不動産などの財産を相続します。法定相続人には以下の範囲があります。
配偶者は常に相続人です。
子供(またはその代襲相続人として孫)も相続人になります。
子供がいない場合、両親や兄弟姉妹が相続人となる場合があります。
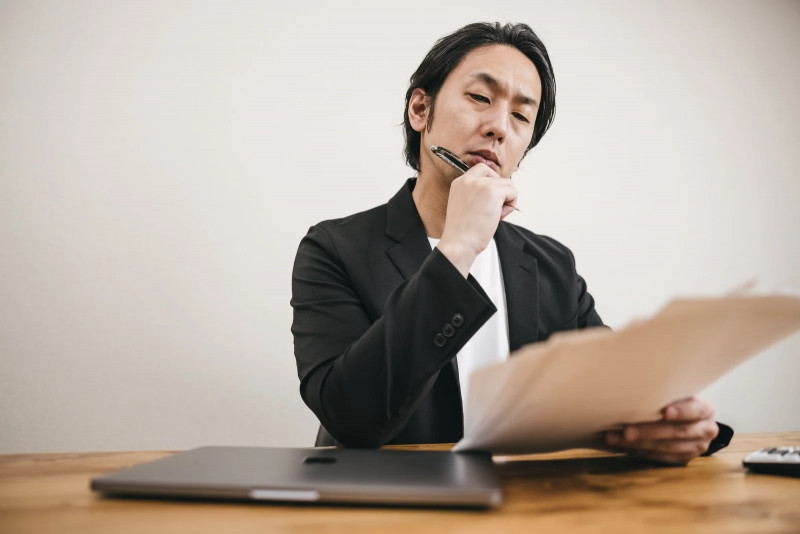
さらに、相続割合も法律で定められており、たとえば、配偶者と子供が相続人となる場合、配偶者が2分の1、残りを子供が均等に分ける形になります。相続人が確定しない限り、次のステップに進むことができないため、相続人の範囲と割合をしっかり把握することが大切です。
相続税は、相続財産が一定の金額を超えた場合に課税されますが、「基礎控除」により、相続税がかからないケースも多くあります。基礎控除は、相続人の人数によって変わるため、自分がどれだけ控除されるかを理解しておきましょう。

基礎控除の計算式
3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
たとえば、相続人が2人の場合、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円となります。相続財産がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
不動産を相続した場合、基礎控除を超える財産に対して相続税がかかります。不動産の評価額を含めた相続財産の総額を基に、段階的な税率で相続税が課されます。相続税の支払い期限は、相続が発生した翌日から10か月以内です。
相続税の税率
相続税の税率は段階的に設定されており、相続財産の金額が大きくなるにつれて税率も高くなります。税率は10%から最大55%まで設定されています。相続税を適切に計算し、期限内に申告・納付することが重要です。
相続した不動産を売却するためには、相続手続きを完了する必要があります。特に、複数の相続人がいる場合、法定相続のルールに従うか、遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決める必要があります。
法定相続とは
法定相続は、法律に従って自動的に相続財産が配分される制度です。これに従えば、不動産の相続もスムーズに進むことができます。
遺産分割協議とは
一方、遺産分割協議は、相続人全員が話し合いで相続財産の分配を決めるものです。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印が必要です。この協議書が完成しない限り、不動産の売却は進められません。
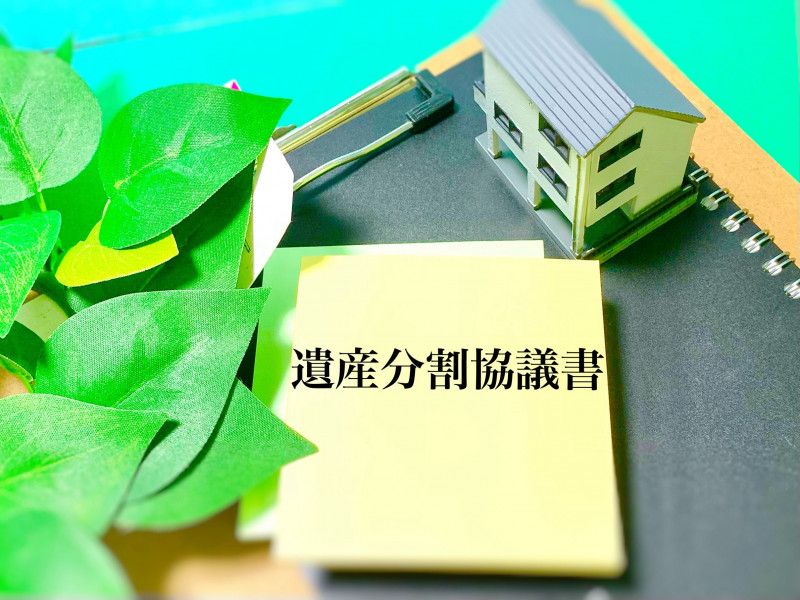
相続した不動産を売却する際、譲渡所得税が発生することがあります。譲渡所得税は、不動産の売却益に対して課税されるもので、売却価格から取得費と譲渡にかかる諸経費を差し引いた額が課税対象となります。
取得費加算の特例
相続した不動産の売却時に利用できる税軽減策として、「取得費加算の特例」があります。これは、相続税の一部を取得費として加算することで、譲渡所得税の課税額を減らすことができる制度です。この特例を活用することで、大きな節税効果が期待できます。
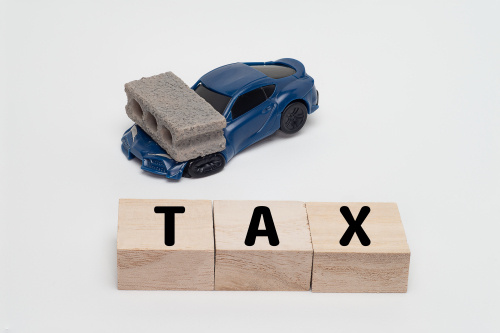
税率の違い
また、売却する不動産を長期保有していた場合(5年以上)、税率は20%と比較的低めに設定されますが、短期保有の場合(5年以内)は39%と高めの税率になります。このため、売却のタイミングを見極めることが重要です。
「長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いについて」はこちら
相続した不動産を売却する際には、相続手続きや税金の知識が不可欠です。この記事で紹介した5つのポイントを押さえておくことで、スムーズに売却を進めることができるでしょう。相続手続きや税務の専門家と連携し、正確な対応を行うことで、最適な結果を得ることができます。相続した不動産の売却を検討している方は、ぜひご参考ください。
相続で取得した不動産売却のご相談は、こちらからお気軽にどうぞ
PDFを開く
1. 相続人とは? 誰が不動産を相続するのかを知ろう
まず、相続が発生すると誰が相続するのかを確認する必要があります。法律により決められた「法定相続人」が不動産などの財産を相続します。法定相続人には以下の範囲があります。
配偶者は常に相続人です。
子供(またはその代襲相続人として孫)も相続人になります。
子供がいない場合、両親や兄弟姉妹が相続人となる場合があります。
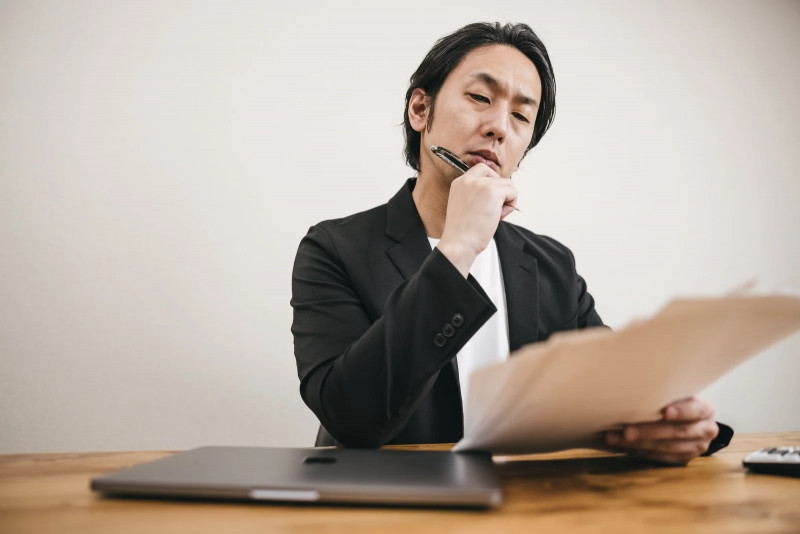
さらに、相続割合も法律で定められており、たとえば、配偶者と子供が相続人となる場合、配偶者が2分の1、残りを子供が均等に分ける形になります。相続人が確定しない限り、次のステップに進むことができないため、相続人の範囲と割合をしっかり把握することが大切です。
2. 基礎控除とは? 相続税の負担を軽減するために知っておくべきこと
相続税は、相続財産が一定の金額を超えた場合に課税されますが、「基礎控除」により、相続税がかからないケースも多くあります。基礎控除は、相続人の人数によって変わるため、自分がどれだけ控除されるかを理解しておきましょう。

基礎控除の計算式
3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
たとえば、相続人が2人の場合、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円となります。相続財産がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
3. 相続税とは? 不動産を相続するときにかかる税金の基本
不動産を相続した場合、基礎控除を超える財産に対して相続税がかかります。不動産の評価額を含めた相続財産の総額を基に、段階的な税率で相続税が課されます。相続税の支払い期限は、相続が発生した翌日から10か月以内です。
相続税の税率
相続税の税率は段階的に設定されており、相続財産の金額が大きくなるにつれて税率も高くなります。税率は10%から最大55%まで設定されています。相続税を適切に計算し、期限内に申告・納付することが重要です。
4. 相続手続きの流れ:法定相続と遺産分割協議の進め方
相続した不動産を売却するためには、相続手続きを完了する必要があります。特に、複数の相続人がいる場合、法定相続のルールに従うか、遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決める必要があります。
法定相続とは
法定相続は、法律に従って自動的に相続財産が配分される制度です。これに従えば、不動産の相続もスムーズに進むことができます。
遺産分割協議とは
一方、遺産分割協議は、相続人全員が話し合いで相続財産の分配を決めるものです。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印が必要です。この協議書が完成しない限り、不動産の売却は進められません。
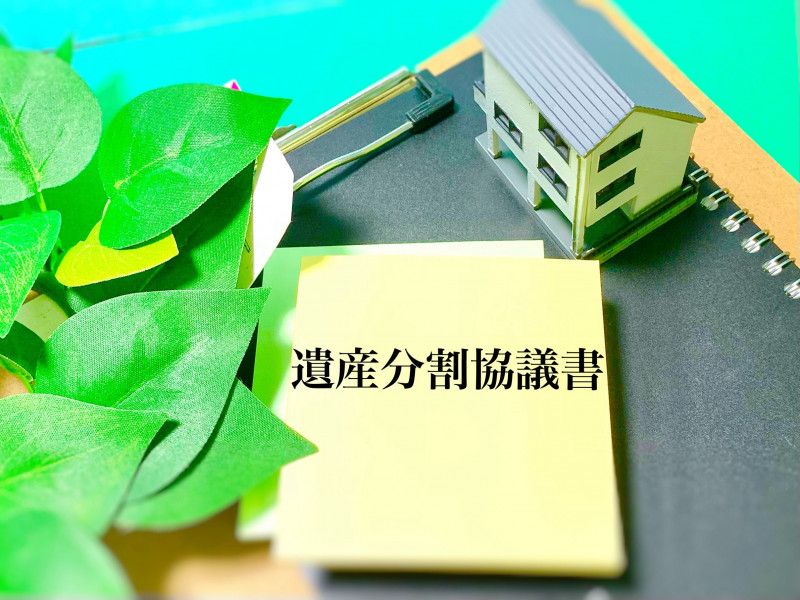
5. 不動産売却時にかかる税金とは? 知っておくべき譲渡所得税の仕組み
相続した不動産を売却する際、譲渡所得税が発生することがあります。譲渡所得税は、不動産の売却益に対して課税されるもので、売却価格から取得費と譲渡にかかる諸経費を差し引いた額が課税対象となります。
取得費加算の特例
相続した不動産の売却時に利用できる税軽減策として、「取得費加算の特例」があります。これは、相続税の一部を取得費として加算することで、譲渡所得税の課税額を減らすことができる制度です。この特例を活用することで、大きな節税効果が期待できます。
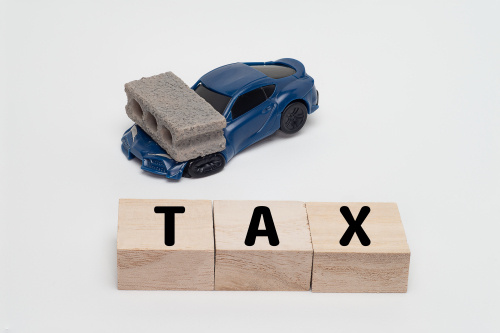
税率の違い
また、売却する不動産を長期保有していた場合(5年以上)、税率は20%と比較的低めに設定されますが、短期保有の場合(5年以内)は39%と高めの税率になります。このため、売却のタイミングを見極めることが重要です。
「長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いについて」はこちら
まとめ
相続した不動産を売却する際には、相続手続きや税金の知識が不可欠です。この記事で紹介した5つのポイントを押さえておくことで、スムーズに売却を進めることができるでしょう。相続手続きや税務の専門家と連携し、正確な対応を行うことで、最適な結果を得ることができます。相続した不動産の売却を検討している方は、ぜひご参考ください。
相続で取得した不動産売却のご相談は、こちらからお気軽にどうぞ


